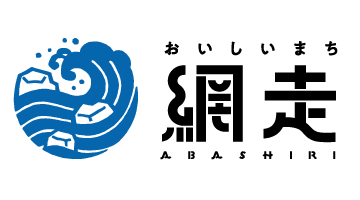本文
限度額適用認定証について
限度額適用認定証とは
高額の診療を受ける場合、世帯の所得状況により、ひと月あたりの自己負担限度額が決まっています。
自己負担限度額を超えてお支払いされた場合については、後日高額療養費の支給申請ができますが、お戻しまで2~3ケ月かかります。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口へ提示することで、当初から窓口の支払が一定の上限額にとどめられます。
また、住民税が非課税の世帯については、入院時の食事代も減額となります。
申請が必要な方
・70歳未満の方
・70歳以上で住民税非課税世帯の方
・70歳以上で住民税課税世帯の方(課税所得145万円以上の方)
(注)70歳以上の方で、住民税課税世帯の方のうち 課税所得が145万円未満の方は自動的に限度額が適用されますので申請の必要はありません。
世帯の所得状況によって申請が不要な場合もございますので、申請の前にお電話でご確認ください。
申請方法
医療保険係の窓口に本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き証明書のうち1点、または資格確認書(保険証)、年金手帳、本人宛郵便物、通帳等のうち2点)をお持ちください。
マイナ保険証で申請不要に
「マイナ保険証」に対応する医療機関において、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、限度額適用認定証がなくても自己負担額をとどめることができます。
(注)直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。