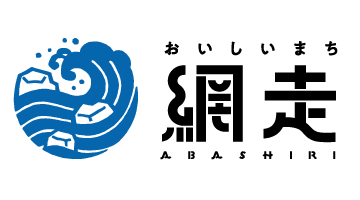本文
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請について
申請免除
市役所の国民年金係や年金事務所に申請し、所得等について審査した結果、経済的な理由などから保険料を納めることが困難と認められたときは、保険料の納付について全額又は一部(4分の3、2分の1、4分の1)の免除を受けられる制度です。(申請者本人・配偶者・世帯主について、所得要件があります)
毎年度(7月~翌年6月)申請が必要です。
内容
免除を受けた期間は、将来年金を受け取るための受給資格期間に算入されます。
免除期間にかかる年金受給額は、免除の種類により2分の1~8分の7(平成21年3月分までは3分の1~6分の5)で計算されます。将来、免除期間分の保険料を納めた(追納)ときは、通常どおり納付した場合と同額の年金を受け取れるようになります。
追納を希望する場合は、過去10年間までさかのぼって納めることができます。その場合は、年金事務所に届出が必要です。
| 免除区分 | 月額保険料 (令和7年度) |
反映される年金給付額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 通常納付した場合の2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,380円 | 通常納付した場合の8分の5 |
| 2分の1免除 | 8,760円 | 通常納付した場合の4分の3 |
| 4分の1免除 | 13,130円 | 通常納付した場合の8分の7 |
一部免除が承認されても、納付しなければならない残りの部分を納め忘れると、未納扱いになってしまいますので、ご注意ください。
退職・失業による特例
失業などを理由に免除を申請される場合には、離職票・雇用保険受給資格者証等の写しを添付することで、失業された方を所得なしとして審査することができます。
納付猶予制度
50歳未満(学生を除く)の方が将来の年金受給権を失わないように作られた制度です。
同居の世帯主(親等)の所得に関わらず、本人と配偶者の所得要件のみによって、保険料の納付が猶予されます。
毎年度(7月~翌年6月)申請が必要です。
納付猶予制度を利用する場合、承認された期間は受給資格期間に算入されますが、将来受給する老齢基礎年金の金額は増えません。申請免除制度と同様、10年以内に追納することで、通常納めた場合と同等の年金額を確保できます。
継続申請
全額免除または納付猶予が承認されたときは、申請時に予め希望を明記しておくことで、翌年度以降も引き続き同じ制度の申請をすることができます。
所得要件を満たさなくなるか、厚生年金や共済組合に加入したり、扶養されたりするまでは、手続きなしで免除を受けることができます。ただし、退職・失業による特例で承認された全額免除・納付猶予については、継続申請することができません。