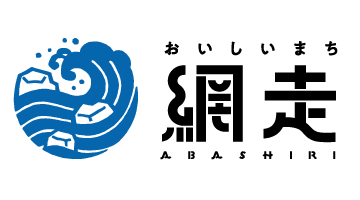本文
所得控除の種類について
雑損控除
災害や盗難等による損失がある場合、控除が受けられます。
以下の計算式により控除額が決まります。
計算式
災害、盗難等による損失額-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等×10%)
医療費控除
医療費の支払がある場合控除が受けられます。
以下の計算式により控除額が決まります
計算式
支払医療費-保険金等で補てんされる金額-(10万円と「総所得金額等×5%」とのいずれか少ない方の金額)
(注)限度額2,000,000円
社会保険料控除
給料や公的年金等から控除された、または直接納付書等で支払った社会保険料がある場合、控除が受けられます。
小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤と結んだ共済契約により支払った掛金(旧第2種共済契約は生命保険料控除)、確定拠出年金法に規定する企業型年金の加入者掛金及び個人型年金の加入者掛金、小規模企業共済法第2条の3に規定する第1種共済契約に基づく掛金および地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金の支払がある場合、控除が受けられます。
生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料の支払がある場合、控除が受けられます。以下の分類に従って控除額が決まります。
| 支払保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 | |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 | |
| 70,000円超 | 35,000円(限度額) | |
| 個人年金保険料 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 | |
| 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 | |
| 70,000円超 | 35,000円(限度額) |
地震保険料控除
(注)平成20年度より創設されました。
地震保険料の支払がある場合、控除が受けられます。以下の分類に従って控除額が決まります。
| 支払保険料 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 地震保険分 | 50,000円以下 | 支払保険料×2分の1円 |
| 50,000円超 | 25,000円(限度額) | |
| 旧損害保険分長期 (注)平成18年末までに締結した長期損害保険料は、従前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。 |
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×2分の1+2,500円 | |
| 15,000円超 | 10,000円(限度額) | |
| 地震保険分及び長期分両方の場合 | (地震保険分で求めた金額)+(長期分で求めた金額) =(最高限度額25,000円) | |
損害保険料控除
(注)平成19年度で廃止
障害者控除(特別障害者控除)
(1)本人、または本人の扶養親族が障がい者であるとき
本人、または本人の扶養親族が障がい者である場合、控除が受けられます。
精神、または身体に障がいのある方で、その障がいの程度が知的障がい者や身体障害者手帳の交付を受けている方に準ずるものとして、市長の認定を受けている方、および戦傷病者手帳の交付を受けている方等を含みます。(2)の特別障害者に該当する場合は、こちらの控除は重複して受けられません。
控除額 260,000円
(2)本人、または本人の扶養親族が特別障害者であるとき
本人、または扶養親族が障がい者で、その人が次のいずれかに該当する場合を特別障害者といい、控除が受けられます。(3)の同居特別障害者に該当する場合は、こちらの控除は重複して受けられません。
- 心身喪失の常況にある方、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により重度の知的障がい者と認定された方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方で、第1級と第2級の方
- 常に就床を要し複雑な介護を要する方
- 精神、または身体に障がいのある満65歳以上の方で、その障がいの程度が重度の知的障がい者、または第1級、第2級の身体障がい者に準ずるものとして市長の認定を受けている方
控除額 300,000円
(3)同居特別障害者であるとき
特別障害者が納税義務者、およびその配偶者または納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況とする方は控除が受けられます。
控除額 530,000円
(注)平成31年度以降、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合、配偶者を扶養親族(控除対象配偶者)とすることはできませんが、配偶者が上記(1)~(3)で掲げた障がい者に該当するときは、障害者控除(特別障害者控除)が受けられます。
ひとり親控除、寡婦控除
ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子を有し、合計所得金額500万円以下のひとり親の方は控除を受けられます。
控除額 300,000円
寡婦控除
夫と死別している、もしくは夫と離別しており子以外の扶養親族を有する、合計所得金額500万円以下の女性の方は控除が受けられます。
控除額 260,000円
勤労学生控除
納税者が勤労学生であるとき控除が受けられます。
(ただし、給与等所得金額が85万円以下で、かつその他所得が10万円以下の方)
控除額 260,000円
配偶者控除
控除対象配偶者があるとき、納税義務者の合計所得金額に応じて控除が受けられます。
ただし、平成31年度以降、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除を受けられません。
控除額(平成31年度以降)
|
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 (一般) |
控除額 (老人) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
|
900万円超 950万円以下 |
220,000円 | 260,000円 |
|
950万円超 1,000万円以下 |
110,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円超 | 0円 |
0円 |
控除額(平成30年度以前)330,000円(老人控除対象配偶者の場合380,000円)
(注)控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)の範囲
市民税・道民税の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にする方(事業専従者を除く)の内、次のいずれかに該当する方
- 前年中に合計所得金額のない方
- 前年中に、合計所得金額が58万円(給与収入のみの方は、収入額で123万円)以下の方(令和8年度以降)
- 老人控除対象配偶者は、上記1か2に該当し、その年の1月1日現在満70歳以上の方をいいます。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)を有する納税義務者で、合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者(平成31年度以降は配偶者及び納税義務者)の所得金額に応じて控除が受けられます。
控除額(令和8年度以降)
| 納税義務者の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
| 58万円超 100万円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
| 100万円超 105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 |
110,000円 |
| 105万円超 110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
| 110万円超 115万円以下 |
210,000円 |
140,000円 | 70,000円 |
| 115万円超 120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
| 120万円超 125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
| 125万円超 130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 130万円超 133万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 |
0円 |
控除額(令和3年度以降)
| 納税義務者の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
| 48万円超 100万円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
| 100万円超 105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 |
110,000円 |
| 105万円超 110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
| 110万円超 115万円以下 |
210,000円 |
140,000円 | 70,000円 |
| 115万円超 120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
| 120万円超 125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
| 125万円超 130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 130万円超 133万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 |
0円 |
控除額(平成31年度以降)
| 納税義務者の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
| 38万円超 90万円以下 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 |
| 90万円超 95万円以下 | 310,000円 | 210,000円 |
110,000円 |
| 95万円超 100万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
| 100万円超 105万円以下 |
210,000円 |
140,000円 | 70,000円 |
| 105万円超 110万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
| 110万円超 115万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
| 115万円超 120万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 120万円超 123万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 123万円超 | 0円 | 0円 |
0円 |
控除額(平成30年度以前)
|
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
| 38万円超 45万円未満 | 330,000円 |
|
45万円以上 50万円未満 |
310,000円 |
| 50万円以上 55万円未満 | 260,000円 |
| 55万円以上 60万円未満 | 210,000円 |
|
60万円以上 65万円未満 |
160,000円 |
| 65万円以上 70万円未満 | 110,000円 |
| 70万円以上 75万円未満 | 60,000円 |
| 75万円以上 76万円未満 | 30,000円 |
| 76万円以上 | 0円 |
扶養控除
扶養親族があるとき、以下の分類に従って、控除が受けられます。
一般の扶養親族(年齢16歳以上の方)
控除額 1人につき 330,000円
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の方)
控除額 1人につき 450,000円
老人扶養親族(その年の1月1日現在満70歳以上の方)
控除額 1人につき 380,000円
同居老親等(同居している老人扶養親族で直系尊属の人)
控除額 1人につき 450,000円
(注)扶養親族の範囲とは
市民税・道民税の納税義務者の親族(配偶者を除く)および児童福祉法の規定による里子ならびに老人福祉法の規定による養護老人で、下記のいずれかに該当する方をいいます。
- 前年中に合計所得金額のない方
- 前年中の合計所得金額が58万円(給与収入のみの方は、収入額で123万円)以下の方
特定親族特別控除(令和8年度以降)
所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、 その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
控除額(令和8年度以降)
| 親族等の合計所得金額(給与収入に換算した金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
(注)給与収入に換算した金額は、収入が給与のみの場合限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。
基礎控除
合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて基礎控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
|
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から控除が受けられます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
【控除額】(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(注)夫婦共働きで双方とも給与等の収入金額が850万円を超え、扶養親族に該当する23歳未満の子がいる場合、扶養親族に係る扶養控除のついてはどちらか一方のみの適用となりますが、所得金額調整控除については、夫婦双方で適用を受けることが可能です。
2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得がどちらもあり、それらの合計金額が10万円を超える場合
【控除額】(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注)1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。