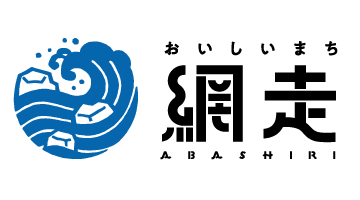本文
所得の種類について
給与所得
給与支払者から支払を受ける給料・賃金・賞与など(アルバイト・パートによる収入を含む)を給与収入といい、その総額から、給与所得控除額(他の所得でいう必要経費に相当するもの)を差し引いた金額を給与所得といいます。
【計算式】 給与収入-給与所得控除額=給与所得
| 給与収入(A) | 給与所得 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 | - |
| 651,000円以上 1,900,000円以下 | A-650,000円 | - |
| 1,900,000円超 3,600,000円以下 | B×0.7-80,000円 | A÷4000×4000=B |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | B×0.8-440,000円 | A÷4000×4000=B |
| 6,600,000円超 8,500,000円以下 | A×0.9-1,100,000円 | - |
| 8,500,000円超 | A-1,950,000 | - |
| 給与収入(A) | 給与所得 | 端数処理 |
|---|---|---|
| 551,000円未満 | 0円 | - |
| 551,000円以上 1,619,000円以下 | A-550,000円 | - |
| 1,619,000円超 1,620,000円以下 | 1,069,000円 | - |
| 1,620,000円超 1,622,000円以下 | 1,070,000円 | - |
| 1,622,000円超 1,624,000円以下 | 1,072,000円 | - |
| 1,624,000円超 1,628,000円以下 | 1,074,000円 | - |
| 1,628,000円超 1,800,000円以下 | C×0.6円+100,000円 | A÷4000×4000=B |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 | C×0.7-80,000円 | |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | C×0.8-440,000円 | |
| 6,600,000円超 8,500,000円以下 | A×0.9-1,100,000円 | - |
| 8,500,000円超 | A-1,950,000 | - |
特定支出控除の特例
特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、給与所得控除額控除後の金額からその超える部分の金額を控除した金額を給与所得の金額とすることができます。
特定支出とは、通勤費、転任に伴う転居費、職務の遂行に必要な研修費や資格取得費等(会社が負担した一定の金額を除く)の合計額などのことです。
事業所得
卸売業、小売業、製造業、サービス業、農業、漁業、その他の事業から生ずる所得のことです。
具体的には、以下のようなものがあります。
営業所得
卸売業・小売業・製造業・建設業及びサービス業などの営業から生ずる所得のことです。
【計算式】 総収入金額-売上原価-売上原価以外の必要経費-青色申告特別控除額=事業所得
農業所得
農作物の生産などから生ずる所得のことです。
【計算式】 総収入金額-必要経費(種苗代・肥料代など)-青色申告特別控除額=事業所得
その他の事業所得
弁護士・医師・芸能人・生花の師匠・ホステス・外交員・作家・畜産業・漁業など営業及び農業以外の事業から生ずる所得のことをいいます。
【計算式】 総収入金額-売上原価-売上原価以外の必要経費-青色申告特別控除額=事業所得
利子所得
預貯金、公社債などの利子、公社債投資信託や貸付信託などの分配金による所得のことです。
必要経費はありません。
原則として所得税15%、住民税5%の割合で天引き(一律源泉分離課税)されるため、申告の必要はありません。ただし、一律源泉分離課税の対象とならない国外の銀行等に預けた預金の利子、世界銀行・アジア開発銀行などの債券の利子所得などは、申告する必要があります。
配当所得
株式の配当、出資の配当、剰余金の分配等による所得のことです。
必要経費として、株式などを取得するために借り入れた負債の利子等を計算します。
【計算式】 配当収入-借入金の利子-外国所得税=配当所得額
平成16年度以降支払いを受ける配当金額が5万円以下(年1回決算の場合には、10万円以下)のいわゆる少額配当に対する個人住民税の取扱いが次のように改正されました。
- 少額配当に係る非課税措置の廃止(平成16年度分の個人住民税から)
- 平成15年4月1日から同年12月31日までの間に支払いを受けた上場株式等の配当については、非課税
(株式会社の発行済株式の総数の5%以上に相当する株式数を有する方がその株式会社から支払いを受ける配当等の大口のものを除く)
不動産所得
家賃、貸事務所、アパート、借地権設定、貸船舶、ネオンサイン設置等により生じた所得のことをいいます。
必要経費として、修繕費、減価償却費、固定資産税等を計算します。
【計算式】 不動産収入-必要経費-青色申告特別控除額=不動産所得
一時所得
生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に生ずる所得のことをいいます。
必要経費として、収入を得るために要した費用等を計算します。
【計算式】
一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除(限度額50万円)=一時所得
(注)上記式で算出された所得金額の2分の1が課税計算の対象となります。
譲渡所得
土地・建物・株・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得のことをいいます。
譲渡所得は所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに分けられます。
土地建物等については、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているかどうか、それ以外のものについては、譲渡する資産を取得した日から所有期間が5年を超えているかどうかで判断します。
【計算式】 譲渡収入-必要経費-特別控除(限度額50万円)=譲渡所得
(注)特別控除は、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得合わせて50万円が限度額です。
(注)土地・建物等の譲渡、株式の譲渡は、他の所得と分離して課税計算します。
雑所得
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得のいずれにも該当しない所得で、公的年金などによる所得や、作家以外の人の原稿料、印税などの所得のことをいいます。
公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入に係る雑所得
【計算式】 公的年金等収入-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得
| 公的年金等収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額による区分 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
| 65歳以上 | 330万円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
| 330万円超 410万円以下 | A×25%+275,000円 | A×25%+175,000円 | A×25%+75,000円 | |
| 410万円超 770万円以下 | A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |
| 770万円超 1,000万円以下 | A×5%+1,455,000円 | A×5%+1,355,000円 | A×5%+1,255,000円 | |
| 1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
| 65歳未満 | 130万円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
| 130万円超 410万円以下 | A×25%+275,000円 | A×25%+175,000円 | A×25%+75,000円 | |
| 410万円超 770万円以下 | A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |
| 770万円超 1,000万円以下 | A×5%+1,455,000円 | A×5%+1,355,000円 | A×5%+1,255,000円 | |
| 1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |
| 年齢 | 公的年金等の収入額(A) | 公的年金等に係る雑所得額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 1,300,000円以下 | A-700,000円 |
| 1,300,000円超~4,100,000円以下 | A×75%-375,000円 | |
| 4,100,000円超~7,700,000円以下 | A×85%-785,000円 | |
| 7,700,000円超 | A×95%-1,555,000円 | |
| 65歳以上 | 3,300,000円以下 | A-1,200,000円 |
| 3,300,000円超~4,100,000円以下 | A×75%-375,000円 | |
| 4,100,000円超~7,700,000円以下 | A×85%-785,000円 | |
| 7,700,000円超 | A×95%-1,555,000円 |
(注)年齢は前年の12月31日現在により判断します。
公的年金等以外の雑所得
【計算式】 公的年金等以外の収入-必要経費=公的年金等以外の雑所得
必要経費として、原稿料等については原稿を書くための調査研究費等を計算します。
雑所得
【計算式】 公的年金等に係る所得+公的年金等以外の所得=雑所得
山林所得
山林の伐採による所得または山林を立木のまま譲渡したことによって生じる所得のことです。
必要経費として、植林費、管理費、伐採費等を計算します。
【計算式】 山林収入-必要経費-特別控除(限度額50万円)=山林所得
(注)山林所得は、他の所得と分離して課税計算します。
退職所得
退職金、一時恩給などによる所得のことです。
【計算式】 (退職収入-退職所得控除)×2分の1=退職所得