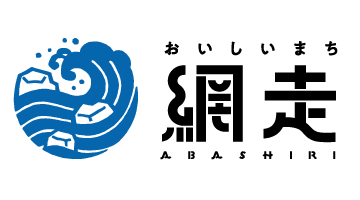本文
令和5年度クラシック音楽鑑賞会事業「弦楽アンサンブル「石田組」 網走公演」
弦楽アンサンブル「石田組」 網走公演

いま最も聴きたいカリスマ・ヴァイオリニスト石田泰尚率いる「石田組」10名が網走で奏でます。この機会にぜひクラシックをお楽しみください!
日時
令和5年10月14日(土曜日) 午後2時00分開演 (午後1時30分開場)
会場
網走市民会館(北海道網走市南6条西1丁目5)
チケット情報
発売日
令和5年6月23日(金曜日) 午前10時より各販売所で取り扱い開始!
(電話受付は6月30日(金曜日)9時より開始)
販売所
エコーセンター2000・網走市民会館・市役所売店・キタノ靴店・フジヤ書店
価格等
一般:3,500円
高校生以下:1,000円
(注)自由席
(注)当日券一般のみ500円増(前売券が完売した場合、当日券の取り扱いはありません)
(注)小学生以上から入場可
プログラム
- シルヴェストリ:バック・トゥ・ザ・フューチャー
- クイーン(松岡あさひ編曲):ボーン・トゥー・ラヴ・ユー
- グリーグ:2つの悲しき旋律 op.34
- ラター:弦楽のための組曲
- バルトーク(ウィルナー編曲):ルーマニア民俗舞曲、ほか
(注)曲目が異なる場合がございます。
その他
演奏の様子はこちらをクリック<外部リンク>
(注)今回の演奏者と曲目とは異なります。
石田組

ヴァイオリニスト石田泰尚の呼びかけにより2014年に結成された弦楽合奏団。
プログラムによって様々な編成で演奏をするスタイルを取っており、メンバーは“石田組長”が信頼を置いている首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーを中心に公演ごとに“組員”が召集される。レパートリーはバロック音楽から映画音楽、プログレッシブ・ロックまで多岐にわたり各々のスタイルをぶつけ合いながら織り成す演奏スタイルは弦楽アンサンブルの新しい世界を切り拓く存在として各方面から注目され2017年にリリースされたアルバム“The石田組”はレコード芸術誌上で特選盤の評価を得た。単独公演のみならず渡辺克也氏、工藤重典氏ら著名な音楽家との共演や組員自ら指導に当たる教育プログラムの実施など活動は多岐に渡る。2018年にNHK-FM「ベストオブクラシック」及びNHK-BSプレミアム「クラシック倶楽部」で紹介されその熱いステージの模様が大きな反響を呼び、2019年にEテレ「ららら♪クラシック」で特集が組まれた。2021年に3年ごとに行われる音楽の友誌クラシック音楽ベストテン、「あなたの好きな室内楽グループ」部門にて第4位(日本人グループ最高位)に選出された。2022/2023シーズンには全25公演となる初のツアーを開催、大好評を博した。2023年4月26日にNewアルバムがユニバーサルミュージックよりメジャー・リリースし全30公演のアルバム発売記念2023/2024全国ツアーも開催中。
(注)今回の公演と出演者、編成が異なります。
石田組出演者プロフィール

石田泰尚(いしだやすなお)
神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、2001年神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来“神奈川フィルの顔”となり現在は首席ソロ・コンサートマスターとしてその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。結成時から20年以上参加するYamato String Quartet、自身がプロデュースした弦楽アンサンブル“石田組”など様々なユニットでも独特の輝きを見せる。2018年には石田組がNHK-FM「ベストオブクラシック」およびBSプレミアム「クラシック倶楽部」で放送されその熱いステージの模様は大きな反響を呼び、2019年にはEテレ「ららら♪クラシック」で特集が組まれた。2020年4月より京都市交響楽団特別客演コンサートマスターを兼任。2022年6月に初の著書となる「音楽家である前に、人間であれ!」を刊行。2023年には石田組のアルバム『石田組 2023・春』、『石田組 2023・夏』を連続リリース。使用楽器は1690年製G.Tononi、1726年製 M.Goffriller。

塩田脩(しおだしゅう)
アメリカ合衆国ボストン生まれ。ジュリアード音楽院プレカレッジを経てニューイングランド音楽院卒業。2010年に来日し、京都市交響楽団ゲスト首席、兵庫県芸術文化センター管弦楽団ゲストコンサートマスター、小澤征爾音楽塾コンサートマスター、水戸室内管弦楽団などを経て。2014年東京都交響楽団に入団。第1ヴァイオリン奏者をつとめる。石田組、トリトン晴れた海のオーケストラ、サイトウキネン・オーケストラメンバー、玉川大学非常勤講師。これまでに潮田益子、田中直子、シャリー・ギブンスの各氏に師事。

伊東翔太(いとうしょうた)
東京音楽大学付属高等学校を経て、同大学を特別特待生として卒業。第27回日本クラシック音楽コンクールアンサンブル部門弦楽器の部第2位(最高位)。2020飛騨河合音楽コンクール第2位(最高位)、それに伴い最優秀者による受賞記念リサイタルに出演。奨学金を得て、ギルドホール音楽院短期留学プログラム修了。小澤征爾音楽塾106に出演。これまでにヴァイオリンを三戸泰雄、篠崎功子、荒井英治、大谷康子の各氏に師事。現在、東京都交響楽団ヴァイオリン奏者。

佐久間聡一(さくまそういち)
山形県出身。幼少よりヴァイオリンを始め、桐朋学園卒業、その後ドイツでも学んだ。
高校時代より、日本青少年オーケストラコンサートマスター、大学時は桐朋学園オーケストラコンサートマスターとして活躍。その後、新日本フィル契約団員、大阪フィル首席奏者、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン客演奏者、広島交響楽団第1コンサートマスターをつとめた。現在は、ソリスト、室内楽奏者として多彩な活動で活躍の幅を広げている。魅力的な音色で聴衆を一つにする力がある」(音楽の友)など誌上でも注目を浴びている。録音多数。「昴21弦楽四重奏団」「弦楽トリオAxis」「ピアノトリオMiyabi」「石田組」メンバー。

田村昭博(たむら あきひろ)
4歳よりヴァイオリンを始める。第45回山口県学生音楽コンクール弦楽器部門第2位(1位なし)。2003年、国立音楽大学ヴァイオリン専攻を卒業。草津国際アカデミーなど数々の音楽祭に参加。2004年に日本フィルハーモニー交響楽団に入団。現在、同団第一ヴァイオリン奏者を務める傍ら埼玉県立川越女子高等学校や浦和ユースオーケストラ等にてトレーナーを務める。これまでにヴァイオリンを故石井洋之助、石井志都子、野波健彦、荒井雅至、石井啓一郎、扇谷泰朋の各氏に師事。

古屋聡見(ふるやさとみ)
桐朋学園音楽学部在学中にN響アカデミーに在籍・修了。ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンに入学。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を始めとする、ドイツ国内の主要オーケストラにエキストラとして参加する。その後セビリア王立管弦楽団にて副首席として半年間期間契約で在籍。現在は日本フィルハーモニー交響楽団、アンサンブル金沢、仙台フィルハーモニー管弦楽団等の国内オーケストラでゲスト首席として出演している。江戸純子、岡田伸夫、ヴァルター・キュスナーの各氏に師事。

小中澤基道(こなかざわもとみち)
長野県諏訪市に生まれ4歳よりヴァイオリンを始める。
洗足学園音楽大学大学院在学中の2007年にヴィオラに転向する。同年、原田幸一郎指揮、洗足フィルハーモニーと共演。2008〜2010年Gmmfsに参加。
これまでにヴィオラを岡田伸夫氏に、室内楽を岡田伸夫、木越洋、安永徹、市野あゆみの各氏に師事する。現在、日本フィルハーモニー交響楽団ヴィオラ奏者、Ensemble il vischio メンバー。
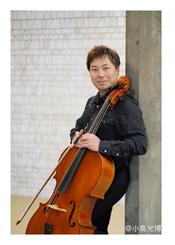
江口心一(えぐちしんいち)
3歳からヴァイオリンを始める。8歳でチェロに転向。1992年フランスのパリ国立高等音楽院に首席で入学。1997年パリ国立高等音楽院で一等賞(プルミエ・プリ)を獲得。2000年より東京都交響楽団団員。現在同交響楽団副首席。ピアノとのデュオ「The Duo」、弦楽三重奏「菖蒲」、ピアノトリオ「東京トリオ」、「トリオナチュール」、「ローズタウントリオ」、弦楽四重奏「Ambition Quartetto」を結成するなど室内楽にも力を入れ、ソロ活動に関してはソロリサイタル、コンチェルトなどこれまでに数々のコンサートで演奏している。
リリースされたCDは「ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲集」「ジャパニーズチルドレンズソング・ヴァイオリン&チェロ」「20世紀の無伴奏チェロ作品」「日本弦楽三重奏曲の世界」「日本弦楽三重奏曲の世界2」「和Cello~無伴奏作品集~」2017年7月Dialogue~涙の理由~。

高木慶太(たかぎけいた)
北海道生まれ。桐朋女子高等学校音楽科(共学)及び桐朋学園大学卒業。同大学院大学を経て’07年春ロームミュージックファンデーションの奨学金を得てベルリン芸術大学に留学。第74回日本音楽コンクール・チェロ部門第2位入賞。ドイツ、ベルリンで開催されたドミニコ・ガブリエリチェロコンクールにて3位位入賞。クァルテット・エクスプローチェ、東京チェロアンサンブル、品川カルテットのメンバー。
米長幸一(よねながこういち)
10歳よりコントラバスを始め、堤俊作氏に師事。桐朋学園大学卒、研究科修了。
在学中に池松宏、ゲーリー・カー、ライナー・ツェペリッツの各氏に指導を受ける。
2000年日本演奏家協会コンクール弦楽器の部第1位。
2001年より神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席コントラバス奏者を務める。
電話予約について
開館日については午前9時から午後7時まで
(注)第1・第3・第5月曜日については休館日のため、午前9時から午後5時までの受付となります。