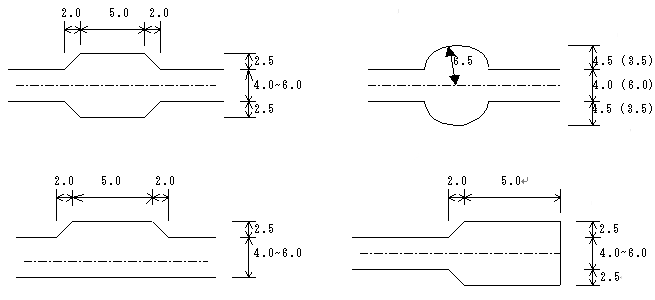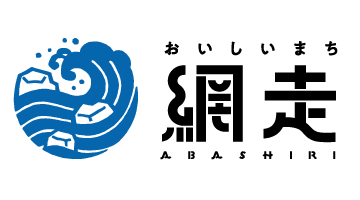本文
道路位置指定基準
網走市道路の位置指定基準
第1「目的」
この基準は、網走市都市計画区域内で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けようとする道路について、その具体的な基準を定めることにより良好な市街地の形成に資することを目的とする。
第2「道路の形態」
位置の指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)の形態については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4及び建設省告示第1837号(昭和45年12月28日)の規定によるほか、この基準に定めるところによる。
ただし、当該道路が公道に接続する場合は、道路法第24条の規定により道路管理者の承認を受けて施行すること。
第3「道路の構造」
指定道路は、砂利敷その他ぬかるみとならない構造で、次の各号により築造するものとする。
- 道路の構造は、上部は砂利または切込砕石40ミリメートル級、厚さ20センチメートル以上とし、下部は火山灰厚さ30センチメートル以上とすること。
- 道路の横断勾配は道路中心線より3%とすること。
- 道路の縦断勾配は12%以下とすること。
第4「指定道路の幅員及び延長」
- 指定道路の幅員は、別図に示す方法によって計るものとし、延長は道路の各部分の中心線によって計るものとする。
- 指定道路の有効幅員は、積雪寒冷地域を考慮し、6.00メートル以上としなければならない。
ただし、地形などによりこれが著しく困難と認められる場合は、この限りでない。 - 指定道路の延長により、道路に付属する土地が明らかに宅地化されると思われる敷地と道路を含めた面積が3,000平方メートルを超えた場合は都市計画法に基づく開発行為の許可が必要となる。
第5「転回広場の間隔」
- 令第144条の4第1項第1号ハの規定による回転広場の間隔は、指定道路の接続する既存道路の側溝(法第42条第2項の規定により道路の境界線がある場合はその境界線)を起点として計るものとする。
- 指定道路の幅員は6.00メートル以下で、道路の延長が35メートルを超える場合は、終端及び区間35メートル以内ごとに自動車の転回広場を設けなければならない。
- 既存の袋路状道路に接続する場合で、当該道路の延長が35メートルを超えるものにあっては、この既存道路にも転回広場を設けなければならない。
ただし、転回広場を設けることが著しく困難と認められる場合で、当該道路に最も近いところに転回広場を設けたときはこの限りでない。
第6「転回広場の規模」
転回広場で、建設大臣が定める基準に適合するものは、次の各号に該当するものとする。
- 小型自動車が2台停車できるものとし1台当りの停車に必要な広さは長辺が5メートル以上、短辺が2.5メートル以上であること。
- 転回広場が長方形である場合は、別図に示すように、その角をはさむ辺の長さが2メートル以上の二等辺三角形の部分を道路に含めて設けることにより、自動車の転回に支障のない形状とすること。
- 転回広場の形状は、別図または、これに準ずるもので、自動車の転回に有効と認められるものとする。
第7「指定道路のすみ切り」
指定道路が同一平面で交差又は接続する場合は、角地のすみを頂点として一辺の長さが2メートル以上の二等辺三角形の部分を道に含むものとしなければならない。
ただし、次の各号の一に該当し、かつ交通安全上支障がないと認められるときは、その部分についてこれを設けないことができる。
- 道路を河川、水路などに接して築造する場合で、これに交差する道路の橋梁、欄干などによりすみ切りができないとき。
- 既存の堅固な建築物、高い堅固な擁壁、若しくはガケ地などがあり、すみ切りを設けることが著しく困難と認められるとき。
第8「指定道路の側溝」
指定道路には側溝を設け、次の各号により築造しなければならない。
- 道路の両側には、コンクリート製U字溝または管渠を設け堅固で耐久力を有する構造とし、溢水のおそれのないものとする。
ただし、地形などにより両側に側溝を設けることが困難な場合は、片側のみとすることができる。
また、U字溝のフタは車道用を使用するものとする。 - 上記の側溝について、U字溝は240ミリメートル以上、管渠は300mm以上とする。
- 側溝に土砂の流入のおそれがある場合または交差、隅角部など適当な箇所に溜桝を設けること。
- 急勾配道路(6%以上)の場合は、路面の侵食及び鉄砲水を防ぐため、横断側溝を適当な箇所に設けること。
第9「排水設備の末端」
側溝及び下水道管などの排水施設の末端は、公共下水道、都市下水路、その他の排水施設の管理者の同意を得てこれに接続すること。
第10「指定道路の維持管理」
指定道路の維持管理は、申請者の責任において地域住民の協力を得て行うようにすること。
第11「指定道路の廃止及び変更」
- 法第43条の規定に抵触する敷地を生じないこと。
- 通り抜け道路の一部廃止は原則として認めない。
- 指定道路の廃止により、路地状となる敷地が生じるときは、路地状部分の使用関係を明確にし、借地の場合は、建築敷地としての使用承諾を得ること。
- 廃止または変更により直接影響を及ぼすと考えられる部分の権利者(家屋の所有者及び使用権者を含む)の承諾を得ること。
第12「特例」
- この基準より難い事情があると認め、その計画が避難及び通行の安全並びに衛生上支障ないと認めるものは、この基準によらないで指定することができるものとする。
ただし、この場合には、申請者はこの基準により難い事情を記載した書面を申請書に添付しなければならない。 - 幅員9メートルを超える道路(将来市道として認定されることが予想されるもの)については、この基準によるほか道路構造令(昭和45年政令320号)の定めによるところにより、計画するよう指導するものとする。
附則
- この基準は昭和58年4月1日から実施する。
- 網走市都市計画区域内における道路の位置指定に伴う宅地造成等の指導要綱(昭和49年5月1日運用)は廃止する。
指定道路の幅員の計り方(基準第4の1)
U字側溝の場合
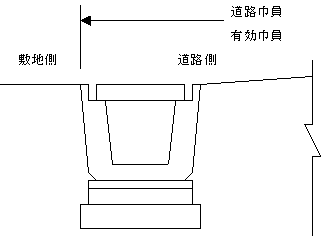
管渠または溜桝を設けた場合
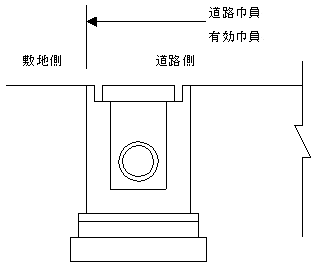
指定道路の計り方(基準第4の1)
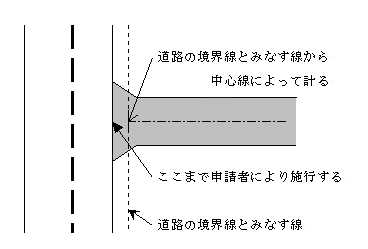
指定道路の延長(基準第4の3)
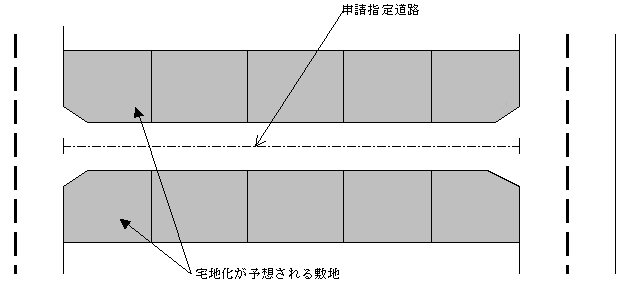
転回広場の間隔(基準第5の1及び2)
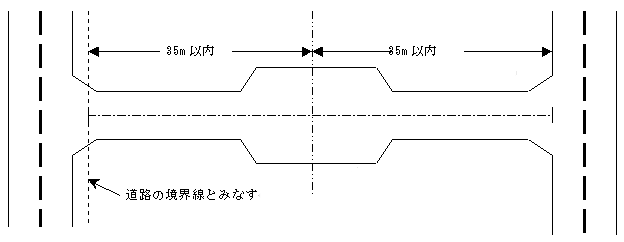
転回広場の間隔(基準第5の3)
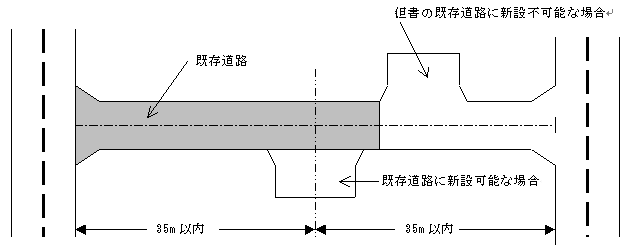
転回広場の規模(基準第6の1及び2、3)