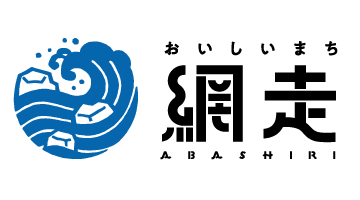本文
令和7年度市政執行方針

1 はじめに
2 市政執行の基本方針
(1)市政を取り巻く環境
(2)当市の財政状況
(3)今年のまちづくりについて
3 主要施策
(1)一人ひとりを大切にするやさしいまち
(2)豊かな自然と共生する安心なまち
(3)ひとが集いにぎわいと活力を生むまち
(4)豊かなひとを育むまち
(5)ともに歩み、ともに築く協働のまち
4 おわりに
1 はじめに
令和7年網走市議会第1回定例会において、予算をはじめ関連する議案をご審議いただくにあたり、市政執行の所信と施策の概要を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
第2期網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略も最終年を迎え、今年度は第3期の戦略が始まる年となります。従来より、戦略を遂行する主体は市民一人ひとりであり、経済社会の大きな流れを掴み、全国の個々の地域ごとに自ら考え、それを練り上げていくものとなります。
国立社会保障・人口問題研究所の統計によると、日本の人口減少を止めることは難しく、コロナショックで、この間の人口動態は約20年早まったことが示されています。出生数、合計特殊出生率、婚姻件数、結婚予定者割合、いずれも減少や低下し、昭和22年、第1次ベビーブームで約270万人だったものが、昨年では70万人を下回るとされるなど、人口減少が進んでいる現実があります。
このことは、網走市においても例外ではありません。シュリンクという不都合な事実は、人口増加を前提とした制度設計ではない、人口減少によるインパクトの緩和と、日本の経済および社会のあり方を変革する好機と捉えるべきものではないかと思います。
やがて世界的に、特に先進国で人口減少局面に入ることを考えると、このことは、人口減少先進国である日本が世界をリードする道でもあり、日本全体が人口減少下にあっても、要因はさまざまあるものの、GDP、個人消費、企業経常利益、国の税収などは増加しているのも現実です。
こうした現況下において、我がまちの利益を喪失しない方策を考え抜き、関係機関、団体など多くの皆様と課題を共有し、より一層の連携を図りながら、市政の懸案事項や課題に機敏かつ柔軟に対応してまいります。
当市においては、働く人材の確保は喫緊の課題であり、地域医療を支える看護師や社会インフラを担う技能者の育成、職場の環境改善に取り組む事業者への支援、新規就職した方への奨励金の支給対象年齢の拡大、看護師、介護従事者、障がい福祉の人材の復職支援や、事業者が行う社宅整備への支援などを実施してきたところであります。
最近の物価の高騰に対しては、市民の日常生活の下支えという観点から、住民税非課税世帯への支援金の給付や、所得税・住民税所得割の定額減税、低所得者世帯への暖房用燃料の支援、市内の登録店で使用できるクーポン券の全世帯への配付、これに加え、子育て世代の負担軽減の観点から、ゼロ歳から高校生までの医療費の完全無償化、1歳までの乳児へのベビー用品購入クーポン券の進呈、小中学校に加え認定こども園、幼稚園、保育園の給食費の無償化を実施してまいりました。
また、自治体新電力会社「あばしり電力株式会社」においては、令和5年から発電を開始した潮見発電所に続き、他の3カ所の発電所において発電が始まり、加えて、本年6月には、NGKオホーツクの発電所も発電を開始いたします。
こうした取り組みにより、市の公共施設で消費する電力の約1割を、再生可能エネルギーへ置き換えられるものと考えており、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、確かな歩みを進めてまいります。
10回目を数えたオホーツク網走マラソン大会は、全国各地から過去最高の約2,800名のランナーが初秋の網走を駆け抜け、東京農業大学の学生をはじめ、市民ボランティアなど多くの皆様のご協力のおかげで、ランニングポータルサイト「RUNNET」において、3年連続の全国1位となりました。改めて、運営に携わってくださった皆様に感謝を申し上げます。
新庁舎建設の議論も平成25年から始まり、さまざまなご意見を賜りながら、令和7年2月25日より業務を開始しました。これを契機として、市民の皆様に親しまれる、より一層、便利になったと思っていただける行政運営に努めてまいります。
今後も引き続き、誰もが健康で安心して暮らし続けられるまちの実現に、全力で取り組んでまいります。
2 市政執行の基本方針
(1)市政を取り巻く環境
政府は、令和7年度予算は令和6年度補正予算と一体として、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」へ移行するための予算と位置づけ、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災、国土強靭化、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、メリハリの効いた予算を通じ、新たなステージへの移行を目指すとしています。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、引き続き経済・財政一体改革を推進するが、「重要な政策の選択肢を狭めることがあってはならない」とし、「経済あっての財政」の考え方の下、生産性向上、労働参加拡大、出生率の向上を通じて潜在成長率を高めるとしています。
国の令和7年度一般会計予算は、過去最大の規模となる115兆5,415億円となり、税収も過去最高の78兆4,400億円と、前年度当初より、約8兆8,320億円の増加となりました。一方、公債依存度は24.8%と改善傾向にあるものの、債務残高はGDPの1.8倍と依然として高い水準にあり、国の厳しい財政状況に変わりはないものと認識しております。
(2)当市の財政状況
当市の財政状況は、これまでの行政改革の取り組みにより、財政の健全度を示す財政指標は改善基調にあり、また、ふるさと寄附の支えにより、一定の基金残高を維持しております。
歳入は、賃上げによる所得増を受け、税収増が見込まれるところです。
一方、歳出では、物価高により全体的に経費が増加する中、子育て支援の充実や地域の活性化、地域医療や地域公共交通の維持・確保、公共施設やインフラ施設の老朽化対策など、様々な市民ニーズに対して、財政規律も保ちながら取り組むことが求められています。
令和7年度の一般会計当初予算は275億7,722万5千円で、対前年度比マイナス7億6,515万4千円、2.7%の減、6つの特別会計は総額で94億7,167万2千円、対前年度比マイナス1億618万4千円、1.1%の減となりました。
また、公営企業会計は3つの事業会計の総額で49億5,323万3千円、対前年度比マイナス9,186万2千円、1.8%の減となったところです。
(3)今年のまちづくりについて
令和7年度は、地域医療や地域公共交通の維持確保、子育て支援の充実、人材の確保、地域経済の活性化など、総合計画を基本として5つの観点からまちづくりに取り組んでまいります。
1つ目は「ひとにやさしく、ひとを育むまちづくり」です。
地域医療では、通院困難者や医師の負担軽減を図る医療MaaSについて、参画医療機関の拡大に取り組むとともに、引き続き、救急医療体制の維持と開業医の誘致に努め、医療提供体制の充実を図ります。
また、従前の「あばしり健康マイレージ」は「あばしり健康ポイント」に改め、参加対象年齢を拡大するとともに、新たにアプリを導入し、自身による健康状態の把握、運動の習慣化を図るほか、引き続き、不妊治療への助成、妊婦と産後の母子に対する支援、健康診査を実施し、市民の健康維持に努めます。
50歳以上のワクチン接種を推奨している帯状疱疹は、定期接種化に伴い接種費用の助成を拡大し、接種の勧奨に努めます。
老朽化が進む網走市総合福祉センターは、旧道立高等看護学院への移転に向け、施設改修の基本設計に取り組みます。
子育て環境では、こども発達支援センターの移転による環境の改善に加え、感覚統合室を新設し、療育機能の強化を図ります。
また、新たに、盲学校と連携した視覚に関する相談体制を構築し、安心して子育てできる環境整備に取り組むほか、子育て世帯の負担軽減のため、高校生までの医療費、小中学校や認定こども園等の給食費の無償化を継続します。
人材の確保では、看護師、介護従事者、障がい福祉従事者の復職に向けた支援に加え、新たに、保育士へも復職支援金を給付します。
学校生活では、児童生徒や保護者に寄り添った適切な対応のため、スクールカウンセラーによる相談体制を充実させるとともに、解決困難な課題に対して各分野の専門家が組織的に対応できるよう、新たに、スクールソーシャルワーカーを配置するほか、特別教室へ電子黒板を整備し学習環境の充実を図ります。
このほか、市内に在住する外国人が、網走の歴史や文化、魅力を学ぶツアーを実施するほか、日本の文化や食文化の体験を通じて市民と交流する機会を創出します。
2つ目は「グリーンなまちづくり」です。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、市民や事業者を対象としたセミナーの開催など啓発活動に取り組むほか、あばしり電力の取り組みでは、NGKオホーツクでの太陽光発電を開始するとともに、さらなる事業展開を図ります。
また、公共施設や公園の照明のLED化を進め、再生可能エネルギーの利用促進と省エネルギー化に努めます。
加えて、森林の環境保全機能の維持のため、植林や伐採など計画的な整備に努め、「こまば木のひろば」では、枯死木の伐採により森林機能の回復を図るほか、森の家や散策路の改修、駐車場の整備など環境整備に取り組み、治山と保健の機能を併せ持つ多目的保安林としての機能の維持を図ります。
3つ目は「活力あふれるまちづくり」です。
農業では、DXの推進、労働力とエネルギー消費の効率化・省力化など、課題に対応する農業者の意欲的な取り組みを支援するほか、近年、急激に増加している有害鳥獣の被害を抑制するため、特にエゾシカの捕獲について集中的に取り組みます。
水産業では、消費者ニーズや商流の変化などに対応する漁業者、水産加工事業者の意欲的な取り組みを支援するほか、漁場環境の保全や、事業者が行う人工種苗養殖試験、海洋環境の変化に対応した漁業を構築するための調査船の整備を支援します。
観光業では、デジタル技術を活用したプロモーションの継続、教育旅行の誘致、網走マラソンをきっかけとした外国人の誘客促進のほか、新たに、酒と食を主軸としたプロモーションや宿泊の増強策により、閑散期の入り込みの底上げを図るとともに、戦略的な観光地域づくりを担うDMOを支援します。
また、令和8年度からの宿泊税の導入に向けた周知に取り組むとともに、これに対応する事業者への支援のほか、デジタルマーケティングで得られた情報などを踏まえた新たな観光振興計画を策定します。
企業誘致では、天都山地区への酒蔵建設予定地の造成を進めるとともに、引き続き、自然災害が少なく夏でも冷涼な気候といった、地域の特性を活かした誘致活動を推進します。
公共交通では、日常の移動手段の確保のため、引き続き、生活路線バスやどこバスの運行支援、郊外地区の乗り合いタクシーの実証運行のほか、新たに、自動運転バスの実証運行に取り組むとともに、地域の最適な公共交通のあり方を示す地域公共交通計画を策定します。
働き手の確保では、これまでの、合同企業説明会、就労や起業への意欲を高めるセミナー、新社会人を対象とした研修会の開催のほか、若年層の人材確保と地元定着を図るため、新規就職した方への奨励金、社会インフラを担う人材確保への支援を継続するとともに、積極的な雇用活動を促進するため、新たに、事業者が行う人材確保の取り組みを幅広く支援します。
また、就労者の住宅確保のため、社宅整備への支援に加え、空き市営住宅の提供戸数を追加します。
物価の高騰に対しては、市内の登録店で使用できるクーポン券を全世帯へ配付し、生活の支援と消費の喚起を図ります。
4つ目は「安全・安心なまちづくり」です。
災害対策では、夜間においても安全に避難できるよう、藻琴地区の津波避難路へソーラー蓄電池式の照明設備を整備するほか、避難所の生活環境の改善を図るため、プライベートテントを整備します。
新たな防災拠点となる新庁舎は、市民が気軽に集える開庁を記念したイベントを開催し、また、建て替えが必要な消防本部庁舎は、レイアウトの検討や、庁舎と外構の実施設計を進めます。
インフラの整備では、道路の改良、橋梁の長寿命化対策、導水管や配水管の布設替え、下水道施設の強靭化を計画的に進めるほか、公園は、遊具の更新を中心とした計画的な再編整備を進めます。
女満別空港網走間の高規格道路は、一日も早い開通に向けて鋭意取り組むとともに、都市機能の集約や公共施設の適正配置などと併せ、都市計画の変更に向けた手続きを進めます。
廃棄物処理では、引き続き、広域での中間処理施設整備に向けた取り組みを進めるとともに、明治最終処分場の埋め立てごみの減量化や嵩上げの検討を進め、その延命を図ります。
住環境では、潮見団地において中層住宅の建設に着手するほか、住宅ストックなどの特性を整理し適正な住宅施策を推進するため、網走市住生活基本計画を策定します。
また、猛暑対策として、中学校と地域子育て支援センターへエアコンを設置するとともに、引き続き、住宅などへのエアコン設置に対しても支援します。
5つ目は「デジタルを推進するまちづくり」です。
災害時の円滑な避難と防災意識の向上を図るため、避難所や避難経路を選定できる機能や多言語に対応した、新たなデジタルハザードマップを作成するとともに、緊急情報や市政情報のメール配信においても、より多くの方に情報が行き渡るよう多言語化を進めます。
また、ごみのポイ捨て状況をAIで可視化する仕組みを導入するとともに、ボランティア清掃の仕組みと併せ、ごみの削減に努めます。
GIGAスクールでは、2期構想の実現に向けたネットワーク環境の整備や1人1台端末の更新に取り組み、個別最適な学びの推進に努めます。
このほか、飲食店の混雑状況をウェブ上で把握できる仕組みを導入し、繁忙期の夕食機会損失の改善を図る取り組み、生成AI時代の到来を見据えた研修の充実や、基幹業務システムの統一・標準化を進めるとともに、工事の電子入札を開始し、入札参加者および市の双方において事務の効率化を図ります。
次に、網走市総合計画に定める将来像「豊かな自然に ひと・もの・まちが輝く健康都市網走」の実現に向けて具体的に取り組む主な施策を、5つの目標に沿って改めて説明いたします。
3 主要施策
(1)一人ひとりを大切にするやさしいまち
第1は、「一人ひとりを大切にするやさしいまち」づくりです。
保健医療
市民の皆様が生涯を通じて健康で安心して暮らせるよう、健康都市連合加盟都市と課題を共有しながら、「網走市民健康づくりプラン」に基づく保健・医療・健康づくりの施策を一体的に推進してまいります。
健康増進では、関係団体と連携した取り組みを進めるとともに、「あばしり健康マイレージ」を「あばしり健康ポイント」に改め、参加対象年齢を拡大するとともに、新たにアプリを導入し、自身による健康状態の把握、運動の習慣化を図ります。
また、50歳以上のワクチン接種を推奨している帯状疱疹は、定期接種化に伴い接種費用の助成を拡大し、接種の勧奨に努めます。
地域医療では、通院困難者や医師の負担軽減を図る医療MaaSについて、参画医療機関の拡大に取り組むとともに、引き続き、救急医療体制の維持と開業医の誘致、人材確保に取り組む医療機関への支援、復職した看護師への支援金の給付のほか、公的病院の高度医療機器の整備を支援し、医療提供体制の充実を図ります。
母子保健では、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない相談体制により、母子の健康保持や増進に努めるとともに、子どもの特性を早期に発見し適切な支援を行うため、新たに、5歳児へ健康診査を実施するほか、不妊治療、不育症治療への助成や産後ケアなど、引き続き、妊婦と産後の母子に対する支援に取り組みます。
地域福祉
地域福祉では、市民の皆様をはじめ団体、関係機関との連携を深め、地域の支え合いを念頭に、安心して生きがいを持って暮らすことができるまちづくりに取り組んでまいります。
老朽化が進む網走市総合福祉センターは、旧道立高等看護学院への移転に向け、施設改修の基本設計に取り組みます。
高齢者福祉では、引き続き、地域および関係機関と情報や課題の共有、連携強化を図りながら、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを切れ目なく一体的に提供する、地域包括ケアシステムのさらなる推進に努めるほか、介護福祉士資格取得に向けた奨学金制度に取り組む事業所への支援や、復職者への支援金の給付などに加え、新たに、外国人材に向けた研修会の開催に取り組み、介護人材の確保に努めます。
障がい者福祉では、手話言語条例に基づく手話の普及啓発、ジョブコーチの養成や資格取得への支援とともに、引き続き、復職者へ支援金を給付し、人材の確保に努めるほか、障がいのある方の希望や能力に合う就労を支援し、関係機関との橋渡しを担う取り組みを進めます。
また、独居高齢者の増加を踏まえ、成年後見制度に基づく的確な支援のため相談員を増員します。
子育て支援では、家事、育児に不安を抱える子育て家庭への訪問支援など、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない総合的な支援を展開するとともに、こども発達支援センターは、移転による環境の改善に加え、感覚統合室を新設し、療育機能の強化を図ります。
また、新たに、盲学校と連携した視覚に関する相談体制を構築し、安心して子育てできる環境整備に取り組むほか、子育て世帯の負担軽減のため、高校生までの医療費、小中学校や認定こども園等の給食費の無償化を継続します。
生活福祉
ひとり親家庭にあっては、引き続き、親と20歳までの子の医療費の一部または全部を助成し、健康保持および福祉の増進を図るとともに、経済的な支援や就労支援に取り組みます。
生活困窮者に対しては、自立相談支援と併せ、世帯全体の家計収支を分析し家計の再生につなげる取り組み、また、就労の準備として基礎能力の形成を支援するなど、自立に向けた支援策を継続します。
(2)豊かな自然と共生する安心なまち
第2は、「豊かな自然と共生する安心なまち」づくりです。
都市空間
市街地での居住および都市機能の集約や適正な配置などを示す「網走市立地適正化計画」に基づく、コンパクトで利便性と持続性の高いまちづくりを推進するとともに、庁舎跡地の利活用、高規格道路の延伸を考慮した都市機能誘導区域内のゾーニングを踏まえ、関係機関と連携を図りながら、都市計画マスタープランの見直しや都市計画の変更に向けた手続きを進めます。
都市基盤
インフラの整備では、道路、橋梁の長寿命化対策、郊外地区の道路整備に取り組むほか、災害に備えた河川の適正な管理に努めます。
公園は、遊具の更新を中心とした計画的な再編整備を進めるとともに、エコーセンター隣接地を取得し、周辺緑地との一体利用を図ります。
冬期対策では、作業車両の更新のほか、積雪深を自動で観測する仕組みを活用しながら、効率的な除雪体制を確保します。
港湾では、網走港の安全な利用のため監視指導を継続するとともに、川筋地区を浚渫し、船舶の安全な航行環境を確保します。
公共交通では、日常の移動手段の確保のため、生活路線バスやどこバスの運行支援、郊外地区の乗り合いタクシーの実証運行のほか、新たに、自動運転バスの実証運行に取り組みます。
JR北海道問題では、乗車運賃の助成や、市民団体などによる自発的な取り組みを支援し、地域利用の促進を図るとともに、鉄路の維持存続に向け、関係団体と連携を図りながら対応します。
また、地域の最適な公共交通のあり方を示す、地域公共交通計画を策定いたします。
女満別空港の利活用では、地域や他空港の関係団体、北海道エアポート株式会社との連携により、路線の増強および利用の促進に取り組みます。
生活安全
市民の安全・安心では、防災イベントの開催や自主防災組織への支援を通じて地域防災力の向上を図るとともに、夜間においても安全に避難できるよう、藻琴地区の津波避難路へソーラー蓄電池式の照明設備を整備するほか、災害時の円滑な避難と防災意識の向上を図るため、避難所や避難経路を選定できる機能や多言語に対応した、新たなデジタルハザードマップを作成するとともに、避難所の生活環境の改善を図るため、プライベートテントを整備します。
新たな防災拠点となる新庁舎は、市民が気軽に集える開庁を記念したイベントを開催し、建て替えが必要な消防本部庁舎は、レイアウトの検討や、庁舎と外構の実施設計を進めます。
交通安全では、運転免許を自主返納した高齢者の移動手段の確保のため、公共交通利用券、どこバス利用券の交付を継続するとともに、園児、児童、老人クラブ会員などを対象にした交通安全教室を開催し、交通安全意識の啓発に努めます。
環境
環境の保全では、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、市民や事業者を対象としたセミナーの開催など啓発活動に取り組むほか、あばしり電力の取り組みでは、NGKオホーツクでの太陽光発電を開始するとともに、さらなる事業展開を図ります。
また、公共施設や公園の照明のLED化を進め、再生可能エネルギーの利用促進と省エネルギー化に努めます。
ラムサール条約登録20周年を迎える濤沸湖では、保全や賢明な利用に向けた意識を育むイベントを開催します。
環境美化では、ごみのポイ捨て状況をAIで可視化する仕組みを導入し、ボランティア清掃の仕組みと併せ、ごみの削減に努めます。
廃棄物処理では、引き続き、広域での中間処理施設整備に向けた取り組みを進めるとともに、明治最終処分場の埋め立てごみの減量化や嵩上げの検討を進め、その延命を図ります。
生活基盤
公営住宅では、潮見団地において中層住宅の建設に着手するほか、計画的な修繕により長寿命化を図ります。
また、より良い住環境づくりに努めるとともに、住宅ストックなどの特性を整理し適正な住宅施策を推進するため、網走市住生活基本計画を策定します。
空き家対策では、空き家バンクを利用した物件の流通の促進や、住宅の解体費用を支援します。
上水道では、安全で安心な水を安定して各家庭に届けるため、導水管や配水管の布設替え、機器の更新に計画的に取り組みます。
下水道では、河川・湖沼の水環境の保全を図る施設の整備のほか、老朽化した機械設備の更新や汚水管の二条化を進め、公衆衛生の向上と施設の強靭化を図ります。
(3)ひとが集いにぎわいと活力を生むまち
第3は、「ひとが集いにぎわいと活力を生むまち」づくりです。
農林業
農業では、持続的な発展と魅力ある農村環境の維持に向け、環境に配慮した安全・安心な農作物生産、農業基盤の整備のほか、農業後継者および新規就農者を対象とした研修への支援など、担い手の確保に努めるとともに、DXの推進、労働力とエネルギー消費の効率化・省力化など、課題に対応する農業者の意欲的な取り組みを支援します。
病害虫や伝染病の対策では、国や道とともにジャガイモシロシストセンチュウのまん延防止と防除に万全を尽くすとともに、家畜伝染病の発生時に迅速に防疫作業が実施できる防疫体制を構築するほか、ヨーネ病の定期検査を実施します。
鳥獣被害対策では、増加する農林業被害を抑制するため、エゾシカの捕獲業務を強化するほか、ヒグマによる人的被害の防止と共生の両立について取り組みを継続します。
林業では、森林の持つ木材生産と環境保全など多面的機能の維持と再生を図るため、計画的な森林整備や林道施設の適切な維持管理に努めるとともに、「こまば木のひろば」では、枯死木の伐採により森林機能の回復を図るほか、森の家や散策路の改修、駐車場整備など環境整備に取り組み、治山と保健の機能を併せ持つ多目的保安林としての機能の維持を図ります。
水産業
水産業では、消費者ニーズや商流の変化などに対応する漁業者、水産加工事業者の意欲的な取り組みを支援するほか、漁場環境の保全、ウニ、シジミ、ナマコ資源の増大対策に加え、海洋環境の変化に対応した漁業を構築するための調査船の整備を支援します。
水産加工の振興では、網走産水産物の良さやおいしさの認知度の向上のため、学校給食や東京農業大学学生食堂での提供、オホーツク網走マラソンや友好都市、首都圏でのPRに取り組むほか、ふるさと納税制度を通じた消費拡大を図るとともに、外国人技能実習生の受け入れや、特定技能1号の外国人材を採用した事業所への支援を強化し、持続的な水産加工業の発展を図ります。
観光
観光では、デジタル技術を活用したプロモーションの継続、教育旅行の誘致、網走マラソンをきっかけとした外国人の誘客促進のほか、新たに、酒と食を主軸としたプロモーションや宿泊の増強策により、閑散期の入り込みの底上げを図るとともに、戦略的な観光地域づくりを担うDMOを支援します。
また、令和8年度からの宿泊税の導入に向けた周知に取り組むとともに、事業者への支援のほか、デジタルマーケティングで得られた情報などを踏まえた新たな観光振興計画を策定します。
商工業
中心市街地の活性化では、網走中央商店街振興組合や網走商工会議所、「まちなか網走」などとの連携によるイベントの開催を通じて、にぎわいづくりに取り組みます。
また、網走桂陽高校の生徒による活性化アイデアの具体化に向け、生徒と関係者によるワークショップを開催します。
企業誘致では、天都山地区への酒蔵建設予定地の造成を進めるとともに、引き続き、自然災害が少なく夏でも冷涼な気候といった、地域の特性を活かした誘致活動に取り組みます。
産業振興
市場開拓・販路拡大では、ふるさと納税制度を通じた特産品のPRに努めるとともに、引き続き、地場産品の生産性向上につながる設備の整備を支援します。
就労対策では、これまでの、合同企業説明会、就労や起業への意欲を高めるセミナー、新社会人を対象とした研修会を開催するほか、若年層の人材確保と地元定着を図るため、新規就職した方への奨励金、社会インフラを担う人材確保への支援を継続するとともに、積極的な雇用活動を促進するため、事業者が行う人材確保の取り組みを幅広く支援します。
このほか、就労者の住宅確保のため、社宅整備への支援に加え、空き市営住宅の提供戸数を追加します。
(4)豊かなひとを育むまち
第4は、「豊かなひとを育むまち」づくりです。
学校教育
小1プロブレムの未然防止に向け、就学前施設から小学校へ円滑に接続させるため、幼児と児童との交流や、教職員が教育内容や指導方法の相互理解を深めるなど、幼稚園、保育園、認定こども園、小学校の連携を進めるとともに、子どもたちの確かな学力、豊かな人間性、健やかな体の調和の取れた成長を促すため、教育内容の充実、学校運営の改善、家庭や地域を含めた教育環境の整備に努めます。
このため、学習支援員を配置し、習熟度別指導や少人数指導などに取り組むほか、引き続き、外国語指導助手による英語教育を実施するとともに、新たに、特別教室へ電子黒板を整備し学習環境の充実を図ります。
また、児童生徒や保護者に寄り添った適切な対応のため、スクールカウンセラーによる相談体制を充実するとともに、解決困難な課題に対して各分野の専門家が組織的に対応できるよう、新たに、スクールソーシャルワーカーを配置します。
加えて、特別な支援を必要とする子どもたちの学校生活や学習活動をサポートする支援員を配置し、個々の状態に応じたきめ細かな支援に取り組むとともに、不登校の児童生徒が通級する教育支援センターにおいても、それぞれの段階に応じた適切な指導に努めます。
さらに、児童の学力・体力の向上を図るため、引き続き、東京農業大学の学生ボランティアによる学習サポート、日本体育大学の指導者による指導や教員研修に取り組みます。
GIGAスクールでは、2期構想の実現に向けたネットワーク環境の整備や1人1台端末の更新に取り組み、個別最適な学びの推進に努めます。
いじめの防止では、学校と家庭・地域における情報の共有や指導体制の充実を図るとともに、未然防止、早期の発見・対応に向け、児童生徒が相談できるアプリの活用のほか、SNSの利用上のトラブルや不登校などの課題に適切に対応するため、引き続き、情報モラルに関する指導に努めます。
また、性に対する正しい知識の習得のみならず、互いを尊重し思いやる心や自己肯定感の育成、コミュニケーションスキルの向上が期待できる包括的性教育を実施し、責任ある選択に必要な知識や、いじめ撲滅の意識醸成を図ります。
生徒数の減少によりさまざまな課題を抱える部活動は、子どもたちが将来にわたりスポーツや文化芸術活動を続けられる環境を構築できるよう、国や北海道が定めるガイドラインに沿って、地域移行に向けた取り組みを進めます。
このほか、すべての教員が子どもたち一人ひとりと向き合う時間を確保できるよう、校務の情報化と効率化を進めます。
高等学校では、網走南ケ丘高校定時制課程の振興や、下校時の通学手段の確保を支援するほか、市内2校の役割、魅力を高める学校づくりなど、望ましいあり方の検討を進めます。
東京農業大学に対しては、地元や友好都市などから入学する学生への学資支援金の給付のほか、都市圏の中学生と高校生を対象とした校外教育プログラムを支援し、さらなる学生確保に努めます。
日本体育大学附属高等支援学校に対しては、引き続き、保護者の経済的負担を軽減するための入学費用、奨学金制度のほか、オープンキャンパスや見学ツアーなどPR活動を支援します。
社会教育
社会教育では、市民の主体的な学びが豊かで潤いのある地域づくりへ進展するような場の充実を図り、網走の魅力を再認識し、新たな発想や創造につながる学習機会を提供する中で、子どもたちの豊かな心や感性、たくましく生きる力を育み、夢を持って生きることの素晴らしさを学ぶ「子ども夢育事業」を引き続き実施するとともに、青少年の学習環境の整備を図るほか、高等教育機関などと連携した多様な学習機会を提供します。
また、人や地域の育成に果たす公民館の機能や役割について意識を高めるため、北海道公民館大会を開催するほか、創立50周年を迎える市民大学では、網走信用金庫創立100周年記念の協賛により特別講座を開催します。
オホーツク・文化交流センターでは、1階トイレを洋式に改修し、混雑の解消と利便性の向上を図ります。
図書館では、各種資料の収集や整備・保存に努め、多くの市民が読書に親しめる環境づくりに取り組むほか、電子図書館へ、ICTを利用した学習ツールとしての機能を追加し、教育現場での有効活用を進めます。
文化
芸術文化では、多くの市民が優れた芸術文化に触れ、豊かな人間性を育むことができる活動の充実に向け、さまざまな分野の芸術文化を鑑賞する機会を提供するとともに、新たなにぎわいを創出し、芸術文化の向上や市民文化の発展につなげるため、恵まれた自然環境など、まちの魅力を活かした合宿誘致により芸術文化の活動拠点づくりを図るほか、音楽・美術の専門家による表現技法の学習機会を提供します。
また、大学対抗の風景写真競技会であるフォトマッチインターカレッジ全国大会を、日本学生写真部連盟との共催により全国で初めて開催します。
このほか、網走信用金庫創立100周年記念の協賛により、札幌交響楽団による演奏会と、SOMPO美術館所蔵作品の展覧会を開催いたします。
博物館では、郷土の歴史について学び体験する場として、企画展の開催や教育普及活動に努めるほか、博物館網走監獄の重要文化財の
耐震化を支援します。
モヨロ貝塚館では、古代モヨロ文化を学び、体験する講座の開催などにより史跡を広くPRし、モヨロ文化の定着を図るとともに、モデルツアーやシンポジウムの開催など、当地域を含むオホーツク遺跡街道としての魅力向上にも努めます。
スポーツ
スポーツでは、競技スポーツの振興はもとより、誰もが生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づくりを進めることができる環境づくりに取り組むとともに、陸上競技場は3種公認に向けた整備を進めます。
また、需要の変化と施設の老朽化に対応したストックの適正化を図るため、総合運動公園内の施設を中心とした再整備構想を策定します。
トップアスリートなどが小学生へ授業を行う「夢の教室」は、対象を中学生にまで拡大し、引き続き、児童生徒の健全育成に取り組むとともに、全道・全国大会に出場するスポーツ少年団への遠征費用の支援は、部活動以外で活動する中学生へも対象を拡大します。
障がい者スポーツでは、障がいのある方がスポーツに親しみ、身体を動かす喜びを体感することによって、健康増進や体力向上を図ることができる環境づくりを進めるとともに、日本体育大学附属高等支援学校や関係団体と連携し、スポーツ教室の開催や指導者の育成を図ります。
スポーツ合宿では、これまでの誘致活動に加え、2026年から秋春制へシーズン移行するJリーグチームに対しても、関係機関や団体と連携を図りながら誘致活動を進めます。
交流
国際交流では、姉妹都市のカナダ・ポートアルバーニ市とは、教育交流訪問団の受け入れやオンラインでの交流など、大韓民国蔚山広域市南区とは、市民の主体的な友好交流の促進を図ります。
また、市内に在住する外国人が、網走の歴史や文化、魅力を学ぶツアーを実施するほか、日本の文化や食文化の体験を通じて市民と交流する機会を創出します。
国内交流では、引き続き、友好都市などと、児童・生徒の体験学習や物産交流などさまざまな交流を進めます。
地域間交流では、網走の食材を扱う市外事業者や、ふるさと寄附をいただいた方々を中心にあばしり応援人・応援隊を募るほか、東京農業大学の卒業生へのアプローチによる関係人口の創出・拡大に努めるとともに、網走での生活を希望する方を大都市圏から募る地域おこし協力隊制度の取り組みに加え、協力隊の活動を短期で体験するインターン制度も活用し、関係人口の増加、移住・定住の促進に努めます。
(5)ともに歩み、ともに築く協働のまち
第5は、「ともに歩み、ともに築く協働のまち」づくりです。
地域協働
地域協働では、市民、地域活動の核である町内会や、さまざまな分野で活動している市民活動団体など多様な組織・団体と連携を深めてまいります。
地域活動では、浦士別地区集落センターの建替検討を進めるほか、町内会や自治会が所有する集会施設の改修経費、団体などの地域活動を支援し、市民活動の活性化やコミュニティの育成を図ります。広報・広聴では、広報紙の充実に努めるほか、緊急情報をはじめ市政情報のメールでの配信は、対応言語を追加し、より多くの方に情報が行き渡るよう取り組みます。
また、「まちづくりふれあい懇談会」「みんなの市長室」「市長への手紙」などの取り組みを通じて市民意識の把握に努め、ともに築く協働のまちづくりを進めます。
行政運営
行政運営では、「網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく効果的な施策を推進するとともに、「網走市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設などの適正な配置や、「第5次網走市行政改革推進計画」に基づく効率的で効果的な事務事業の推進、「網走市DX推進計画」に基づく持続可能なまちづくりに努めます。
また、地域公共交通、観光・空港の振興、地方創生、廃棄物処理など、一基礎自治体では解決が困難な課題に対しては、自治体、大学、企業、団体などと多様な連携を図りながら解決に取り組み、東オホーツク定住自立圏においては救急医療体制の維持、広域による廃棄物中間処理については、美幌町を加えた1市5町により、圏域全体で必要な生活機能を確保するための取り組みを進めます。
4 おわりに
新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に変更になったのは、2023年5月8日でした。2020年の春に新型コロナウイルス感染症が日本を覆い、その後、まん延防止要請、緊急事態宣言などが発せられ、日常生活では人と人との距離を取り、友人との会食はせず、入院をした親類を見舞うこともできず、酒場は午後8時以降の営業自粛が要請されるなど、社会が止まったことを初めて経験した約3年でした。
つい、1年少し前の出来事です。
コロナ禍は、その副産物として急速なデジタル化をもたらし、農村地区では光回線の整備が促進され、児童生徒一人ひとりにパソコンが貸与されるなど、劇的に進んだ時でありました。
一方、人と接触することが躊躇される社会を背景に、この間、我が国の人口減少は、当初より20年早く進んだことも事実です。人口減少社会を生きる私たちは、この不都合な事実と向き合いながら、地域をつくり上げていかなければなりません。
「ブラジルの一匹の蝶の羽ばたきは、テキサスで竜巻を引き起こすか?」と、1972年に気象学者エドワード・ローレンツ氏が講演した「バタフライエフェクト」は、私たちの小さなまちにもその示唆を与えています。
ほんの小さな選択が、想像を超える未来をつくり出すかもしれない。それは世界のどこかで誰かを笑顔にするかもしれないし、このまちを大きく変えるかもしれない。蝶の羽ばたきが、地域を変える力になるかもしれない。混沌とした社会の中で、予測困難性、初期値鋭敏性は、バタフライエフェクトとして、世界が複雑につながっていることを教えています。
小さな取り組みを、小さな気付きを重ねることが、このまちを持続可能とし、大きな変化を生み出す種まきであることを信じて、まちづくりを精一杯、推進してまいります。
今後とも、市民の皆様の市政に対するご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。