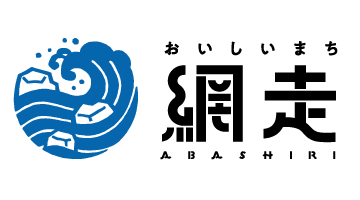本文
市営住宅入居者の方に気を付けてほしいこと(結露・カビ対策)
どんな場所で結露は起きやすいのか
結露とは、温度差により空気中の水蒸気が水滴となる現象をいいます。
色々な環境・条件があるため、一概には断定できませんが、おおよそ次のようなことがいえます。
- 家具の配置などにより、空気の流れにくい住宅
- 湿度の高い住宅
- 南側よりも北側が発生しやすい
結露とカビ・ダニは密接な関係があるといわれています。
また、結露の発生する箇所には必ずカビが発生するもので、適切な結露対策はカビ・ダニ防止に直結してるといえます。
湿度を意識する
機密性の高い北海道の住宅で、部屋を閉め切り換気をせず、冬場ポータブルのストーブを使用したり、ストーブ上でヤカンのお湯を沸かしたりすると、部屋のどこかで結露が発生していると考えて間違いありません。
室内で発生した水蒸気が空気中に溶けきらなくなると、余った水分は床や壁、サッシやガラスの表面に付き、結露の原因を作っていきます。
また、押入れやクローゼットは換気をしても空気の入れ替えが非常に少なく水蒸気を滞留させる場所の代表といえます。
住宅内の温度を制御する事は、北海道の季節変化を考えればとても難しいものです。
ですが、結露・カビ・ダニに共通している湿度を制御することはある程度可能です。
住宅内湿度を低く保つことで、快適に生活できるのと同時に結露・カビ・ダニも発生しにくくなります。
日常生活で行なえる結露・カビへの対策
水蒸気が発生するものは、換気も併用する
お料理をする、洗濯物を干す等、室内で水蒸気が発生する要因は様々です。
そのような時は必ず換気扇を利用するようにしましょう。その時に窓を少し開けて吸気口を造っておくと尚、効果的です。
また、換気扇はその発生源の近くで回すことが重要です。
たとえば洗濯物は浴室で浴室換気扇を回しながら干す。
リビングの窓側で多少の日差しを浴びさせて干すのであれば、窓をほんの少し開けてリビングの換気扇をまわす。
このような些細な事で、大きな効果が生まれる事もあります。
押入・クローゼットの換気
晴れた日には時々押入やクローゼットを開け、中の空気を入れ替えて下さい。
長期間、扉を閉めっぱなしにすると中に滞留した水蒸気は逃げ場がなく露点以下の温度で結露となります。
当然ですが、結露は内壁だけではなく押入に収納してある布団や衣服にも発生し、その結果カビが発生する原因になります。
サッシの結露
サッシのガラス部は外気と室内気の温度差によってとても結露が発生しやすい場所です。
掃除をしていないホコリやチリの溜まったサッシが結露すると、カビの発生率がぐんと高くなります。
サッシのこまめな拭き掃除(結露水のふき取り)が重要です。
室内の湿度管理が十分でなければ何度でも再発してしまいます。
浴室のカビ
市営住宅には色々なタイプの浴室がありますので一言ではいえないのですが、共通して言える重要な事は換気とふき取り、入浴中に飛び散った泡や石鹸水などを洗い流すことです。
高温多湿の浴室はカビにとって絶好の発育環境になります。上記方法以外に基本的な対策はありませんが、最後の入浴者が、使用直後に壁やドア等にシャワーで冷水をかけて浴室内温度を下げると共に、飛び散った泡などを洗い流すことが効果的です。
こまめな室内掃除
室内のホコリやチリはカビの発育には欠かせない栄養素です。
室内湿度をコントロールすると共に、室内の清掃をこまめにしてカビの栄養素をなくすことはとても重要なことです。
冬のポータブルストーブや加湿器は大敵です
屋外と煙突でつながっていないポータブルストーブは、燃焼中室内に大量の水蒸気を発生させています。また加湿器も、その名の通り室内に水蒸気を送っています。
これらは就寝などで機器の使用を止め、部屋の温度が下がると、大量の表面結露を発生させます。
使用中は外気との温度差で結露を発生させ、使用後は室内温度が露点を下回り壁紙などに表面結露を起こす、といったサイクルができあがりカビを発生させる原因となります。
ポータブルストーブの使用は厳禁です。
また、加湿器の使用後は換気を徹底しましょう。
最後に
近年住宅のカビやダニは、アレルギーや呼吸器疾患の原因となることが判明しています。
また、結露やカビは住宅の寿命を縮める原因にもなります。
結露等でお悩みの方は前述の通り、日常生活でほんの少し意識をしていただくことで改善される可能性があります。
入居されている皆様にはご理解とご協力いただきまして、快適な生活を送っていただけますよう宜しくお願いいたします。